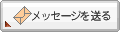2008年04月21日
中津三丁目を知ろう
★ 中津3丁目とはどんなところか
JR・阪急・淀川に囲まれた、十三大橋南東に位置する数百世帯の小さな町。
分断されたような位置のため都市開発者側から見ても旨みがなく、
淀川堤防に沿って高速道路延長の計画はあるものの一般幹線道路は1丁目(RAMADA・三井アーバンホテルの向い)、5、6、7丁目(阪急中津西口からスカイビルの手前まで)
に集中したため住宅地内には都市計画道路がない。工場・運輸・商業地帯への運送ルートにも当らないので騒音もない。
繁華街からは離れており治安も悪くない。
市の調査でも、大阪市北部(中央大通より北)で昭和中期の町並みが密集して残っている地域はこの中津3丁目だけとされている。
長屋と路地が構成する懐かしい雰囲気は家屋が朽ち果てるまで残り続ける。
梅田の都心部から路線距離1km、直線距離500mという位置にあってこれは奇跡的な条件と言える。
(遮断してくれた線路と堤防には感謝するほかない…)
現在行われている大阪駅北側、旧JR貨物駅を中心とする24haの通称「北ヤード開発」の第1期街開きは2011年。(最終、第2期は2015年と言われている)
大都市開発が阪急中津駅を挟んで反対側までせまることで、歴史を持った町としての貴重性はさらに高まるだろう。
*****
中津という地名と大体の場所は関西人なら誰でも知っているでしょうが、
3丁目の町並みを知っているのは地域住民とまだ一部の人達だけのようです。もったいない。
住民の方の多くはこの町がいつまでも残っていくことを望んでいます。
高層化・都市化で希薄になっていくばかりの人間関係、壊れていく街ではなく町と人との関係もここにはごく普通に、演じているわけではなく日常の風景としてあります。
北区内を下町探しにくまなく歩こうと思って2ヶ月目、偶然ここを見つけたとき一番驚いたのは、古くからの町にありがちな閉鎖性がないこと、
盛り上げたいという意欲があること、それに期待していること。
まちづくりとか町おこしは一部の、実は根本には閉鎖性を持った矛盾行動のマニアがするものではない。
その意味ではここは住民全体が、子供に至るまで、プロデューサと言える。
これがわかった瞬間からもう場所はここ以外に考えられない。となってこの計画をスタートさせた。
地域そのものと一体になって盛り上げていきたい。もっと良くする。何を良くするのか?では悪かったことは何なのか?そんなことも考えながらやっていきたい。
実際にそういう課題もたくさんあるから。
回りを見ずに一人でやっていくのは適さない。というかそういう人はここには来ないが。
相乗効果という言葉がまるごとキーワードになる。
そして何より、知らなかった人にここを教えたい。
変わったな言い方をすればこの昭和の町を知って現在の生活に生かして実感してなお勉強して好きになってしまいには居ついてほしい。
それに、アート活動にはこういう町が一番似合う。
なんでかって、話す人がいくらでもいるから。
JR・阪急・淀川に囲まれた、十三大橋南東に位置する数百世帯の小さな町。
分断されたような位置のため都市開発者側から見ても旨みがなく、
淀川堤防に沿って高速道路延長の計画はあるものの一般幹線道路は1丁目(RAMADA・三井アーバンホテルの向い)、5、6、7丁目(阪急中津西口からスカイビルの手前まで)
に集中したため住宅地内には都市計画道路がない。工場・運輸・商業地帯への運送ルートにも当らないので騒音もない。
繁華街からは離れており治安も悪くない。
市の調査でも、大阪市北部(中央大通より北)で昭和中期の町並みが密集して残っている地域はこの中津3丁目だけとされている。
長屋と路地が構成する懐かしい雰囲気は家屋が朽ち果てるまで残り続ける。
梅田の都心部から路線距離1km、直線距離500mという位置にあってこれは奇跡的な条件と言える。
(遮断してくれた線路と堤防には感謝するほかない…)
現在行われている大阪駅北側、旧JR貨物駅を中心とする24haの通称「北ヤード開発」の第1期街開きは2011年。(最終、第2期は2015年と言われている)
大都市開発が阪急中津駅を挟んで反対側までせまることで、歴史を持った町としての貴重性はさらに高まるだろう。
*****
中津という地名と大体の場所は関西人なら誰でも知っているでしょうが、
3丁目の町並みを知っているのは地域住民とまだ一部の人達だけのようです。もったいない。
住民の方の多くはこの町がいつまでも残っていくことを望んでいます。
高層化・都市化で希薄になっていくばかりの人間関係、壊れていく街ではなく町と人との関係もここにはごく普通に、演じているわけではなく日常の風景としてあります。
北区内を下町探しにくまなく歩こうと思って2ヶ月目、偶然ここを見つけたとき一番驚いたのは、古くからの町にありがちな閉鎖性がないこと、
盛り上げたいという意欲があること、それに期待していること。
まちづくりとか町おこしは一部の、実は根本には閉鎖性を持った矛盾行動のマニアがするものではない。
その意味ではここは住民全体が、子供に至るまで、プロデューサと言える。
これがわかった瞬間からもう場所はここ以外に考えられない。となってこの計画をスタートさせた。
地域そのものと一体になって盛り上げていきたい。もっと良くする。何を良くするのか?では悪かったことは何なのか?そんなことも考えながらやっていきたい。
実際にそういう課題もたくさんあるから。
回りを見ずに一人でやっていくのは適さない。というかそういう人はここには来ないが。
相乗効果という言葉がまるごとキーワードになる。
そして何より、知らなかった人にここを教えたい。
変わったな言い方をすればこの昭和の町を知って現在の生活に生かして実感してなお勉強して好きになってしまいには居ついてほしい。
それに、アート活動にはこういう町が一番似合う。
なんでかって、話す人がいくらでもいるから。
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン